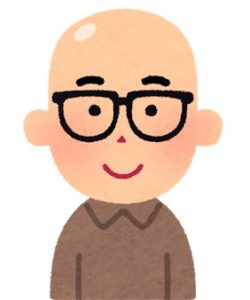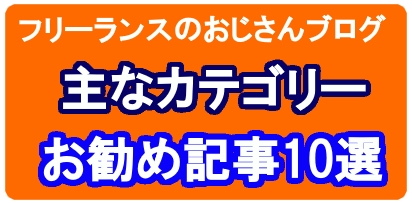環境変化に対応する生き方・考え方
 ダメになっていく会社は、結局環境の変化に対応することができなかったというのが大きな理由です。
ダメになっていく会社は、結局環境の変化に対応することができなかったというのが大きな理由です。
例えば、昔は地方都市にも百貨店がありました。でも今では、見かけることはほとんどなくなりました。
多くの百貨店は環境の変化に対応できなかったから淘汰されたのです。
一個の人間も環境の変化に対応して生きていかないと、淘汰されてしまう時代になりました。
いままでは、個人が所属する会社・組織が対応してくれていて、一個人がそんなことを考えなくても済んだのですが、もうそんなことを言っていられる時代ではなくなりました。
今回はそんなことを考えて、この記事を書いています。
この記事を読むと、個人が環境変化に対応していくにはどのような生き方、考え方をしていけば良いのかわかるようになります。
Contents
中小企業診断士の視点:環境変化に対応する生き方・考え方
記事の内容
|
この記事は中小企業診断士のKAZUTOYOが書いています。
年寄りの言うことをうのみにするのは危険
- 年寄りは昔の価値観で生きている
まず、年寄りは昔に生きていた人なので、価値観が若い年代の人とは違っているというのがあります。
また、昔の常識を正しいと考えているということもあります。
それらが、現代に通用すれば良いのですが、そうでないことが多いのが事実です。
ですから、彼らの言うことをうのみにして、それに従うことは危険なのです。
ビジネスにもそれは言えます。
アマゾンが存在しないビジネス環境での成功体験は通用しない
昔、商売をやっていて成功した人の多くは、リアルの店舗での成功です。昔はそのやり方で成功したかもしれないですが、その時にはアマゾンはなかったのです。今の時代に通用するかはわかりません。
今は店舗がなくても、ものが売れる時代です。昔の商売の常識は通用しなくなっているのです。
今の時代はインターネットのバーチャル店舗と競争しなくてはいけませんが、そのノウハウは彼らにはないのです。
モノを欲しがらない若者が増えている
また、価値観も変化しています。
今はミニマリストなどといって、できるだけモノを持たないシンプルな生活を好むような人が増えています。
昔は、ぼろアパートに住んでも高い車をローンで購入する人がいましたが、モノを持つということに関して、強い欲求を持つ人が昔より少なくなっているような気がします。
考え方が変化しているのです。
このような変化のなかでは、年寄りの常識や価値観はもはや時代遅れになっていて、彼らのいうことをうのみにすることはリスクなのです。(KAZUTOYOも年寄りの年代にさしかかっているのですが)
やっかいなのは、彼らは悪意がなく良かれと思って意見を言ってくることです。
ITを使わない経団連
 出典:https://www.huffingtonpost.jp/entry/keidanren-pc_jp_5c5d84c6e4b0974f75b36e24 より
出典:https://www.huffingtonpost.jp/entry/keidanren-pc_jp_5c5d84c6e4b0974f75b36e24 より
このようなことがニュースになるのです。これが経団連トップです。時代についていけるのかと思ってしまいます。
真偽のほどはよくわかりませんが、もしあなたが会長の立場だったらどうでしょう。
パソコンぐらい用意してよ、と言うと思いませんか。過去の会長はパソコンなしで会長業務を行っていたということでしょうか。
このような常識がまだまかり通っているのです。
年寄りの言うことをうのみにするのはやめましょう。
若者から学ぶようにする
- 凄い若者が多くいる
最近、ユーチューブ動画を見ていて思うのは、しっかりした考えを持つ非常にかしこい若者が多いことです。動画の質も高いです。
KAZUTOYOは彼らの動画を見て学ぶことが多いのです。刺激にもなります。
というか、KAZUTOYOが学ぶのは自分より若い人がほとんどです。
彼らは月に数百万以上稼いでいる人が多いのですが、生活はシンプルなのが多いです。
物欲もあまりないようです。
KAZUTOYOの年代の人は、豊かな生活をするために仕事をして稼ぐという考えかたが主流だったと思いますが、若い人はそういうわけではないようです。
ユーチューブ動画を見ているといろいろ勉強になります。これからも若い人の動画を見て勉強していきたいと思っています。
マスコミの言うことも間違っていることが多い
- マスコミは間違っている
昔は、テレビでいっていることは正しい。ニュースは正しい、と思っていました。でもインターネットでいろいろな情報に触れるようになると、そうでもないこともわかってきました。
ちょっと前も、企業はお金を内部にため込んでいてずるい、というような論調で話を進めている番組を見ました。それは企業会計の仕組みを知らないからそうなるのですが、何か番組の意図が感じられる内容でした。
企業の内部留保については当ブログ「中小企業診断士の視点:企業の内部留保にあたる利益剰余金が過去最高」と「中小企業診断士の視点:企業の内部留保(利益剰余金)は増え続けるのが普通」のページに書いています。
興味のある方は、ご覧ください。
インターネットの情報は、玉石混合だと言いますが、そんなことはわかっているのでいいのです。でもテレビや新聞のニュースが間違っているとは、KAZUTOYOのような昔の年代の人はあまり思なかったのが本当のところだと思います。
でも、インターネットのおかげで、テレビやマスコミの情報が間違っていることがわかってきました。
結構でたらめなことを平気で、さも真実かのように放送しているのです。
結局はインターネットの情報が正しかったということもあります。
このように、テレビや新聞など、従来昔の人にとっては信頼できるソースだと考えていた媒体が、実はそうではないということがばれてきたのも、大きな変化です。
テレビや新聞などのマスコミ情報も、うのみにはできないということが分かったのです。
事実が明るみになり、過去の常識をくつがえす時代
- 調査や技術が進むと、常識がくつがえります
昔の常識だったことが、時代が進むとその常識がくつがえることが多くあります。
調査や技術の進展のおかげです。
KAZUTOYOが昔教科書で習ったことが、実は間違っていたということがあります。
- 日本で一番古い貨幣は「和同開珎」ではない
例えば、日本で一番古い貨幣です。KAZUTOYOは「和同開珎」が最も古い日本の貨幣と学校で習いました。
でも、違うのです。日本で一番古い貨幣は「富本銭」という貨幣です。
調査研究の結果、そうわかったのです。
この話は、当ブログ「中小企業診断士の視点:一円玉の流通量は何枚あるのか?」でも書いています。よろしかったら、ご覧ください。https://kazutoyoblog.com/distribution-of-one-yen-coins/
- 縄文時代にも水田で稲作を行っていた
また、縄文時代と弥生時代の大きな違いは、稲作をしていたかどうかの違いと習いました。縄文時代はクリなどの植物の採集と動物の狩猟によって食糧をまかなっていたと、ずっと思ってきました。
稲作を始めたのは弥生時代で大陸の人々が日本に来て稲作を始めたのが始まりで、それを境にして縄文時代と弥生時代に分けている、となんとなく(そう習っていたことが頭に残っていて)そう思っていました。
ですが、それが間違っていると解ってきたのです。
佐賀県唐津市の菜畑遺跡で紀元前930年頃の水田跡が見つかったのです。
紀元前930年頃は縄文時代です。(一般的には紀元前300年頃から弥生時代のようです)
ということは、縄文時代には水田があり、稲作が既に行われていたということです。
詳しいことは、ウィキペディアの「菜畑遺跡のページ」に書かれています。
大陸の人がきて日本に稲作を伝え、それから弥生時代になったという従来の定説は間違っていることがわかってきたのです。
ただ、それだと矛盾が生じてしまうので、最近は弥生時代の始まりを従来の紀元前300年頃から紀元前900年~紀元前1000年頃からにしようと画策しているようです。
関わっている年寄りの研究者達が、自分たちの研究の間違いを認めたくないからです。いろいろなしがらみもあるのでしょう。なにか強引のような気がします。
でも、ウィキペディアの菜畑遺跡のページにも書かれているように、科学的にも証明された事実なのです。
このように、これかも調査や技術の進展で事実が明らかになり、過去の常識がくつがえることが出てきます。
KAZUTOYOは良い時代になったと思います。
逆に過去にしがみついている人は、これから苦しい時代になるではないでしょうか。
まとめ
まず、年寄りは昔に生きていた人なので、価値観が今とは違っているというのがあります。また、昔の常識を正しいと考えているということもあります。それを押し付けようとする人もいるので注意しましょう。
最近、ユーチューブ動画を見ていて思うのは、しっかりした考えを持つ非常にかしこい若者が多いことです。彼らから学ぶことが多いのです。
昔は、テレビでいっていることは正しい。ニュースは正しい、と思っていました。でもインターネットでいろいろな情報に触れるようになると、そうでもないこともわかってきました。
昔の常識だったことが、時代が進むとその常識がくつがえることが多くあります。 |