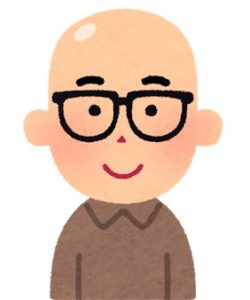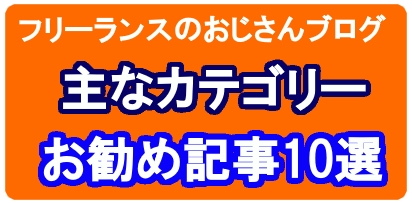合理的な組織作り—組織原則
企業や会社は人の集団組織です。
そして組織には組織を合理的に編成する原則があります。
今回は組織の原則 組織原則の話です。

そんな疑問にお答えします。
この記事を読むと、企業や会社の組織の原則についてわかるようになります。
Contents
合理的に組織を編成する組織原則
本記事の内容
|
この記事は中小企業診断士のKAZUTOYOが書いています。
- KAZUTOYOは家電量販店店員(サラリーマン)として10年以上の経験があります。
- 中小企業診断士としての活動歴10年以上の経験があります。
組織原則とは
- 組織を合理的に編成するため
企業や会社は人の集合体です。
集団の中の人が自分の考えで個々に勝手に動くと、集団としての力が発揮できません。
そこで、経験的に考えだされてきたのが組織原則です。
組織原則は組織を合理的に編成することで、集団としての力が発揮できるようにします。
組織原則は人間が経験を重ねることによって、考えだされてきた・発見されてきた原則なのです。
代表的な組織原則
- 5つの原則があります。
代表的な組織原則は5つあります。
- 命令一元化の原則
- 統制範囲の原則
- 専門家の原則
- 権限正規に対応の原則
- 階層短縮化の原則
それぞれについて簡単に紹介します。
①命令一元化の原則
組織を秩序正しく維持するためには、命令系統の一貫性が保たれている必要があります。
そこで、組織内のすべての人はただ1人の上司から命令を受けるようにするのです。そうなれば命令系統の一貫性は保たれます。これが、命令一元化の原則です。
②統制範囲の原則
1人の監督者が物理的にコントロールできる部下の数には限界があります。その範囲を越えると管理の能率は低下することになります。
統制できる範囲に部下の数を決めるということです。
統制範囲の原則はスパン・オブ・コントールともいわれます。
③専門家の原則
仕事はなるべく同じ種類のものにまとめて分割し、これを担当する人が同質の活動に従事できるようにします。こうすることで、仕事は効率よく回るようになります。
これを専門家の原則といいます。
④権限責任対応の原則
組織内の各担当者は職務を担当するのにふさわしい権限と、それに対応する大きさの責任を担う必要があります。これを権限責任対応の原則といいます。
⑤階層短縮化の原則
組織の階層は数が少ないほど効率が上がるという原則です。
組織原則への批判
- 矛盾がある
組織原則への批判もあります。
H.サイモンらは、組織原則が意味するところがあいまいで、相互に矛盾するものもある。ことわざのようなものにしかすぎない、としています。
まとめ
|
合理的に組織を編成する組織原則
組織を合理的に編成するための原則です
代表的な組織原則は5つあります。
相互に矛盾するものもあるという批判もあります。 |