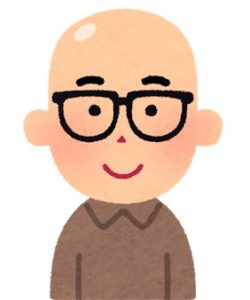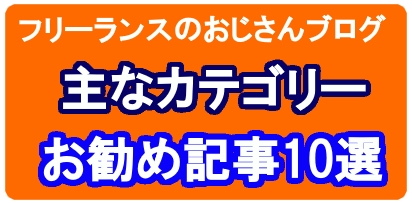大企業病とは何?
 若い方で就職を控えている方もいるでしょう。
若い方で就職を控えている方もいるでしょう。
大企業に就職しようと思っている方も多いと思います。
そんな方の中でも「大企業には『大企業病』というのがあると聞いたことがある。『大企業病』っていったなんだろう」と疑問に思っている方も多いと思います。
今回は、そのような方の疑問にお答えします。
Contents
中小企業診断士の視点:大企業病とは何ですか?
記事の内容
|
この記事は10年以上の中小企業診断士活動歴のあるKAZUTOYOが書いています。数多くの中小企業の経営支援の経験を持っています。
また、地元商工会議所の商工調停士でもあります。
今回は、これから就職を考えている方に、大企業特有の『大企業病』について知っておいてもらうためにこの記事を書くことにします。
あらかじめ、そのようなことがあると知っていると、大企業に就職した後「なるほどな」と思うこともあると思います。
大企業病とは大まかにいうと何なのか?
- 企業規模が大きくなり、成熟化してきて、次第に硬直化してくることによる弊害のこと
企業規模が大きくなって年月が経過すると、組織が次第に成熟していきます。
すると、次第に組織自体が硬直化していきます。内部の変化を嫌うようになっていくのです。
例えば、大きな組織では業務を効率よく回していくために、様々なルールができていきます。
ですが、次第にルールを守ることが目的となっていくのです。
ルールも時代によって変化させていくのが良いのですが、なかなか変化していかないのが大きな組織の特徴です。
組織自体が変化を嫌うのです。
企業内でも重視される「はんこ」の文化は、その典型例だと思います。
具体的にはどのようなことがあるのか?
- 5つあります。

- 組織の硬直化
- リスクを回避する風土
- トップが現場を掌握できない
- 組織内政治の横行
- 不要なポストが増える
①組織の硬直化
ルール・手続きが常識となり、意思決定が多段階となり決定するのに時間がかかるようになっていきます。
②リスクを回避する風土
組織を構成する人がそれぞれ、失敗するのを回避するようになります。
その結果、チェレンジする行動は抑制され、あたりさわりのない提案が横行するようになります。
③トップが現場を掌握できない
いわゆる「奥の院」的な存在が生まれます。
その結果トップが嫌がるような情報は届かず、前線で起こった問題の内、トップが喜ぶような都合のよい情報だけがトップに伝わるようになります。
④組織内政治の横行
組織内でいかに力を持つか、そして力を与えられるかが最大のインセンティブとなるため、権力を維持することに集中するようになります。
⑤不要なポストが増える
管理部門が肥大化します。
経営を勉強すると役に立ちます
- 経営の勉強は社会に出て役立ちます
中小企業診断士の勉強をしている時、思ったことがあります。
もっと早く勉強しておけばよかったと。
実際にサラリーマンで仕事をしていると、今、目にしていることはあの本に書いてあったことだ、というように気が付くことがあるのです。
例えば、KAZUTOYOがいたのは大企業ではないのですが、先ほどの大企業病のような事象は一部起こっていたのです。
経営学は「実学」なのです。実学とは実生活に役立たせることを趣旨とした学問のことです。
経営学は社会にでて働く人にとって生きていく上で役立つ学問です。
早いうちに、経営について学んでおくことをお勧めします。
マネジメント検定(経営学検定)
中小企業診断士の資格取得は目指さない、または中小企業診断士の勉強はハードルが高いと思っている人にも、お勧めできるのが「マネジメント検定(経営学検定)」です。
書籍も充実しているので、じっくり学べます。体系的に学べるのが良いと思います。
まとめ
|
大企業病とは何ですか?
企業規模が大きくなり、成熟化してきて、次第に硬直化してくることによる弊害のこと
等です。
|