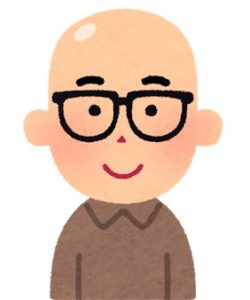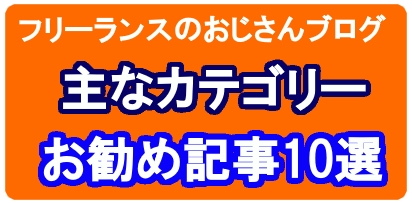粉飾決算って何?その手口とは?
 粉飾決算という言葉は誰しも耳にしたことがあると思います。ですが、内容については良くわからない方もいるでしょう。
粉飾決算という言葉は誰しも耳にしたことがあると思います。ですが、内容については良くわからない方もいるでしょう。そんな方のために、今回は粉飾決算について、その手口など理屈も含めてお伝えしていきます。
この記事をよむことで、粉飾決算を行う理由やその手口などについてわかるようになります。
Contents
粉飾決算の手口とは?
記事の内容
売上高を水増しする方法(2つあります) 費用を過小に見せる方法(2つあります)
|
粉飾決算とは何?
粉飾決算という言葉は、誰しも聞いたことがあると思います。
粉飾決算とは、利益を水増しして儲かっているように見せかけることです。
粉飾決算を行う理由
なぜ、粉飾決算を行うのかというと、外部の利害関係者に儲かっているように見せたいからです。
粉飾決算は株式を上場している会社でよく問題になります。
上場会社は業績が悪いと株価に影響します。株価が下がると、株主は株を持っていてもしようがないので、売りに出します。そうなると、ますます株価の下落につながります。
ということなので、それを防ぐために利益を大きく見せたいのです。
- 逆粉飾とは
逆に利益を過小に見せることを逆粉飾といいます。脱税の手段として行われことが多いです。税金は利益額に応じて納税額が決まりますから、税金をなるべく少なくしたい会社は逆粉飾にして、利益が出ていないように見せかけるのです。
粉飾決算の手口
ここでは粉飾決算の手口についてみていきます。
粉飾には売上高を水増しする方法と費用を過小に見せる方法の2つがあります。
理由は次の式を見ればわかります。
利益=売上高-費用
利益を高めるには、売上高を高めるか、費用を低くするかの2つの方法になります。粉飾ということですから、売上高を実際より水増しする方法、費用を過小に見せる方法ということになります。
それぞれについて見ていきます。
売上高を水増しする方法
①架空売上を計上する
架空の売上を計上することで、売上を水増しします。
これは簡単にできます。年度末などに売掛金という形で売上を計上するのです。
②前受金を売上として計上する
前受金は、「商品代金として」その一部または全部を前もって受取った場合に使用する勘定科目です。
仕分けは (借方 )現金 (貸方)前受金 となり、売上は立ちません。
ですが、(貸方)現金 (貸方)売上 のようにして売上として計上します。
費用を過小に見せる方法
利益=売上高-費用ですが、費用は、売上原価、販売費及び一般管理費、営業外費用の3つに分解できます。
利益=売上高-(売上原価+販売費及び一般管理費+営業外費用)となります。
①売上原価を過小に見せる方法
このうち手口としてよく使われるが、売上原価を過小に見せる方法です。売上原価を過小に見せる方法としては、期末商品棚卸高を過大にする方法がよく使われます。
売上原価というのは売上げた商品の原価という意味です。これを過小に見せるのです。ちょっと難しくなりますが、売上原価は以下のようにして求めるのが一般的です。
売上原価=期首商品棚卸高+当期商品仕入高―期末商品棚卸高
そして売上原価を過小に見せる方法で、よく利用されるのが、期末商品棚卸高を過大にする方法です。
期末商品棚卸高が大きくなれば、売上原価は小さくなるのです。
ちょっとやってみます。
とすると、売上原価は1000万円です。
とすると、売上原価は900万円です。 |
利益=売上高-(売上原価+販売費及び一般管理費+営業外費用)
上の式で売上原価を少なく見せかけることができ、利益が高くなることがわかります。
②未払費用を計上しない
本来は本年度分の費用ですが、まだ支払っていない費用があります。そのような費用は未払費用という負債にして次年度に繰り越していって、次年度振替仕分けを行います。
本年度中に費用にして、利益から差し引かないといけないのですが、この費用を計上しないのです。
費用が少なくなるので、利益をその分多く見せかけることができます。
このようにして、粉飾決算は行われるのです。
まとめ
粉飾を行う理由は、外部の利害関係者に利益が得られているように見せたいから。特に上場会社は株主に配慮する必要があり、そのような行動をとってしまうことがあります。
|
粉飾決算の手口
架空売上を計上する 前受金を売上として計上する
売上原価を過小に見せる方法として、期末商品棚卸高を過大にする方法がよく使われます。このほか未払費用を計上しないという方法もあります。 |